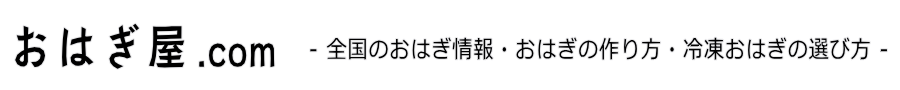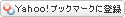おはぎの作り方
おはぎの商品設計と作り方

手作りおはぎといっても、どこまで自店で製造できるかにより、以下の3通りございます。
- あんこ製造・生地製造
- あんこ仕入・生地製造
- あんこ仕入・生地仕入
ここでは「あんこ仕入・生地製造」の参考手順を掲載させて頂きます。
商品設計
総重量、あんこ・生地比率の決定
重量、あんこ生地比率をお店のコンセプト、客層、販売価格、味、競合商品等を考慮し、
決定してください。
最近の傾向だとあんこ比率は6~7割。
参考)なごみやのマーケットリサーチデータ
(会員登録すると会員サイトで数多くのおはぎのデータをみることができます:無料)
ただし、サイズやあんこ生地比率は、あんこの選定次第で調整が必要になります。
あんこの選定
あんこは、候補となるあんこで食べ比べするのが一番ですが、その際に選ぶ主なポイントは
以下の2つになります。
- 甘さ控えめ
仕入れるあんこのBrixを確認してください。
最近の傾向だとBrix40~50。
参考)なごみやのマーケットリサーチデータ
(会員登録すると会員サイトで数多くのおはぎのデータをみることができます:無料)
- 小豆の産地・品種
甘さ控えめなあんこは、小豆そのものの味わい・風味がそのままでてきますので
産地、品種が何を使用しているか確認してください。
- 毎年の作柄によって味・色は変化しますが、産地・品種が異なるとあんこの味、風味はかなり変わってきます。
- 産地や素材の訴求をされる場合は、最終決定後に産地証明書を頂いておくことをおすすめします。
- 砂糖の種類によっては、食べはじめの甘さと食べた後の甘さが変わってきますので要チェックです。
1.生地の製造
炊飯と蒸しの2通りありますが、今回は、作りやすい炊飯での製造方法になります。
米選び
もち米100%の生地もあれば、1~2割うるち米を入れる生地もありますが、
うるち米を3割以上配合すると、ご飯っぽさがでてきます。
地元のお米や銘柄にこだわった訴求をする方もいらっしゃいます。
地域性や作り手の好みで配合割合を決めてください。
炊飯
必ず3時間以上浸漬させてください。翌朝炊飯する時は、前日の夜から浸漬させます。
- 水の量は、もち米はうるち米よりも水を吸わないため、うるち米を炊くよりも少なめにして下さい。
- 炊飯ネット(ご飯ネットやライスネット等)を使うともち米が釜にこびりつくのを防ぐことができます。
- その日のうちに生地が固くなるのを防ぐ場合、柔らかい状態を保つために、炊飯時に糖蜜をいれて炊くことも方法のひとつです。
- 浸漬をせずに、すぐに炊飯できる補助剤もあります。ご希望の方はお問い合わせください。
味付け
炊きあがった生地をある程度冷ましてからそのまま計量する場合は味付けは不要です。
ここでは、参考までに、砂糖、塩で味付けをする例をあげさせて頂きます。
- 炊きあがった生地の重量に対して、水40%、砂糖15%、塩0.5%をかき混ぜながら沸騰させます。(柔らかめの配合です。お好みで配合割合を変更して下さい)
- ボール等で生地とよく混ぜ合わせ、耐熱性ビニール・ラップをかぶせて約1時間寝かせ、浸透させます。※一度上下を混ぜあわせるとムラが少なくなります。
2.計量
あんこ・生地をそれぞれ計量し、成形します。
目分量で行っているところも多いのですが、基本的には電子はかりを使用します。
のせる面が広い電子はかりを使用すると、連続して数個計量することができます。
簡易計量の方法

- あんこは、アイスクリームのディッシャー(※番号で容量が異なります。)を利用し、効率的に計量することができます。
- 最初の数個は、電子はかりで、すり切り具合を確認してどのぐらいか確かめることをおすすめしています。
- 生地は、寿司シャリ玉やたわらおむすびなどに使用している押し型を使って、一つの型全体の量目分の生地を計量し、型にはめて成形することができます。
- さらに生地玉の製造効率を高めるためには成型機を使用する方法もございます。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
3.成形
さまざまな形がありますが、代表的な形は、たわら型、丸型、舟底型があります。